
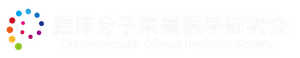

この商品はすでに無効です。 ホームページに戻る

足りないのは
サプリではなく知識です
開校からの総受講者数3,542名
医師・歯科医師 763名
薬剤師・看護師・管理栄養士449名
ファスティング・トレーナー130名
卒業生の栄養外来開設、セミナー開催 多数
© 2025分子栄養学実践講座運営事務局
© 2025臨床分子栄養医学研究会
規約と条件
プライバシーポリシー

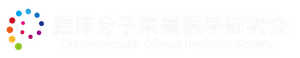


足りないのは
サプリではなく知識です
開校からの総受講者数3,542名
医師・歯科医師 763名
薬剤師・看護師・管理栄養士449名
ファスティング・トレーナー130名
卒業生の栄養外来開設、セミナー開催 多数
© 2025分子栄養学実践講座運営事務局
© 2025臨床分子栄養医学研究会